撉傒暔僔儕乕僘
洕擜偺廘偄偺婰壇
抧揷丂廋堦丂巵
栚師
1丏偼偠傔偵
2丏廘偄偺婰壇偲偦偺昞尰
3丏壠偺拞偱偺廘偄
4丏媯庢傝帪偺廘偄
5丏奨妏偱偺廘偄
6丏敤偱偺廘偄
7丏偍傢傝偵
丂廘偄偺婰壇偼姶忣揑偐偮抐曅揑偱偁傞偑備偊偵丄摼偰偟偰濨枂偵側傝偑偪偱偁傞丅洕擜偦偺傕偺傗僩僀儗偺廘偄偼晄夣偲姶偠傜傟傞偑丄歬妎偵偼屄恖嵎偑偐側傝偁傝丄傑偨梋傝偵傕擔忢揑偱偁傞偑備偊偵丄婰榐椶偵偼傎偲傫偳婰弎偝傟偰偄側偄丅偨傑偨傑丄洕擜傗僩僀儗偺廘偄偵晀姶側曽乆偑彂偄偨帺暘巎傪偄偔偮偐擖庤偡傞偙偲偑偱偒偨丅杮曬崘偼丄偙傟傜偺暥復昞尰傪斺業偡傞偲偲傕偵丄廘偄偵娭偡傞擇丄嶰偺暥專偐傜摼偨抦尒傪徯夘偡傞傕偺偱偁傞丅
僉乕儚乕僪丟洕擜丄廘偄偺婰壇丄廘偄偺昞尰丄埆廘丄廘偄偺帺暘巎
1丏偼偠傔偵
丂15擭傎偳慜偵拠娫偲丆堦弿偵弌斉偟偨亀峕屗丒搶嫗偺壓悈摴偺偼側偟亁乮搶嫗壓悈摴巎扵朘夛曇丄媄曬摪弌斉丄1995乯偺僾儘儘乕僌偱昅幰偼偙傫側偙偲傪彂偄偨丅
丂乽偦偺崰丄壠偺掚偼崱偱偄偆壠掚嵷墍偲偟偰巊傢傟偰偄偨丅巹偺曣偑擾壠偺弌恎偱偁偭偨偨傔偐丄栰嵷偺旍椏偲偟偰帺暘偱洕擜傪媯傒庢偭偰梌偊偰偄偨丅悘暘廘偄偑偟偨偱偁傠偆偲巚偆偑丄巹偺婰壇偵偼巆偭偰偄側偄丅偨偩丄怴慛側僉儏僂儕傗僫僗傗僩儅僩傪偍傗偮偺戙傢傝偵怘傋偨偙偲傪丄傛偔妎偊偰偄傞丅乧
丂彫拞妛峑偺僩僀儗傕媯庢傝幃偱偁偭偨丅乮拞妛峑偱偼乯僩僀儗偺憒彍偼摉斣惂偱惗搆偑峴偭偰偄偨丅傾儞儌僯傾廘偺偡傞廘偄僩僀儗偱丄乧
丂偙偺崰丄僨僷乕僩側偳偺戝宆揦曑偑恑弌偟偰偒偨丅偦傟傜偺揦偵偁傞媞梡偺僩僀儗偼悈愻壔偝傟偰偄偨丅墂慜偵偁偭偨岞廜僩僀儗偲偼塤揇偺嵎偺偒傟偄偝偱偁偭偨偺偱丄傛偔棙梡偝偣偰傕傜偭偨丅乧
丂嫹偄戭抧撪偵偁傞擫偺妟傎偳偺壠掚嵷墍偵嶵偄偨媯庢傝洕擜偺廘偄偑婰壇偵巆偭偰偄側偄堦曽偱丄彫拞妛峑偺僩僀儗偺廘偄傗墂慜偺岞廜僩僀儗偺報徾偼傓偟傠慛柧偱偁傞丅壗屘偩傠偆偐丅昅幰偩偗偺偙偲側偺偩傠偆偐丅偙傫側敊慠偲偟偨媈栤偑摢偺嬿偵堷偭偐偐偭偰偄偨丅
丂擔忢惗妶偵偁傑傝偵傕枾拝偟偰偄傞偣偄偐丄摼偰偟偰僩僀儗偵娭偡傞婰弎偼彮側偄丅偄傢傫傗丄偦偺廘偄偵尵媦偟偨傕偺偼傎偲傫偳尒摉偨傜側偄丅偦偆偟偨側偐偱丄洕擜偺廘偄偵姶庴惈偺嫮偄曽乆偑彂偄偨帺暘巎揑側僄僢僙僀傪偨傑偨傑撉傓婡夛偑偁偭偨丅偦傟偼亀傆傞棦怣廈恴朘亁乮崅嫶弐晇挊丄捁塭幮丄1992乯偱偁傝丄亀恖偼側偤擋偄偵偙偩傢傞偐抦傜側偐偭偨擋偄偺晄巚媍亁乮懞嶳掑栫挊丄KK儀僗僩僙儔乕僘丄1989乯偱偁傞丅
丂杮曬崘偼丄偙傟傜偺曽乆偺洕擜偺廘偄偵偮偄偰偺婰壇偲偦偺暥復昞尰傪斺業偡傞偲偲傕偵丄偄偔偮偐偺暥專偵帵偝傟偰偄傞廘偄偵娭偡傞抦尒傪徯夘偡傞傕偺偱偁傞丅
2丏廘偄偺婰壇偲偦偺昞尰
2亅1丂廘偄偺婰壇
丂僸僩偺姭妎偼丄
丂乽恖娫偼偄偔傜搘椡偟偰傕丄尰嵼旲偺慜偵懚嵼偟偰偄側偄僯僆僀傪丄摢偵巚偄婲偙偡偩偗偱偦傟傪姶偠傞偙偲偼偱偒側偄丅乧丂擼偺拞偱姶妎偑愯椞偟偰偄傞峀偝偼丄帇妎偑戞堦偵戝偒偔丄歬妎傗枴妎偼偦傟偵斾偟偰偼傞偐偵嫹偔丄敪払偺掱搙傕掅偄丅偟偨偑偭偰丄婰壇偺撪梕傕朢偟偄偲偄偊傞乿丄偦偺偆偊乽暥柧偺敪払偼歬妎傪撦姶偵偝偣偨丅乧恖娫偺歬妎偑旀楯偟堈偄偙偲偼傛偔抦傜傟偰偄傞丅埆廘偵巚傢偢巭傑偭偨屇媧傕丄傗傓側偔彮偟偢偮嵟掅尷搙偵峴偭偰偄傞偲丄傗偑偰壗傕姶偠側偔側偭偰暯婥偱屇媧偟埆廘偺偙偲傪朰傟偰傎偐傤偙偲偵峫偊傪扗傢傟偰偟傑偆乿乮亀扱妎偺榖亁乮崅栘掑宧挊丄娾攇彂揦丄1974乯偲偄偆庛揰傪帩偭偰偄傞丅
丂偝傜偵丄壃栰梞堦偼亀偦偙偑抦傝偨偄擋偄偺晄巚媍亁乮梇寋幮丄1993乯偺拞偱丄歬妎偺敪払偵娭偟偰丄
丂乽僩僀儗偺偵偍偄偼偡傋偰偺恖偵嫟捠偺晄夣廘偱偁傞偲偄偭偰傕夁尵偱偼側偄偑丄恖娫偼杮棃丄僂儞僐偺偵偍偄偑寵偄偱偼側偄偙偲偑嵟嬤偺尋媶偱傢偐偭偰偒偨丅歬妎偺敪払偼丄偼傗偔偐傜偼偠傑傝丄梒帣偱傕偐側傝偝傑偞傑側偵偍偄傪姭偓暘偗傞偙偲偑偱偒傞丅偟偐偟丄偙偺偙傠偵偼傑偩僂儞僐偺偵偍偄傪寵偆孹岦偼偁傜傢傟側偄丅僂儞僐偽偐傝偱側偔丄傎偐偺埆廘偵傕寵埆傪帵偝側偄偺偑傆偮偆偱偁傞丅偲偙傠偑丄偳傫側偵抶偔偰傕廫屲嵨偔傜偄傑偱偵偼丄堦條偵僂儞僐偺偵偍偄傪寵偑傞傛偆偵側傞偲偄偆丅偦傟偼丄僂儞僐偼墭偔偰廘偄傕偺偲嫵堢偝傟偰堢偭偨寢壥側偺偩丅偮傑傝屻揤揑側傕偺偩偲偄偆偙偲偵側傞乿
偲弎傋偰偄傞丅
丂偲偙傠偱丄歬妎偵偼偙傫側晄巚媍側堦柺偑偁傞丅偦傟偼丄
丂乽偄偐側傞埆廘傕丄偦偺擹搙偑婬敄偵側傟偽丄晄夣偺姶忣偼婲偙傜側偔側傝丄帪偵偼丄夣偄僯僆僀偲側傞傕偺偝偊偁傞丅阬崄僕僇偐傜庢傝弌偟偨暘斿態帺懱偼晄夣側暢廘傪傕偭偰偄傞偑丄偙偺僯僆僀傪婓庍偟偰偄偔偲丄傗偑偰壔徬昳偺庡懱偲側傞傛偆側丄偊傕偄傢傟偸傛偄僯僆僀傪惗偠傞傛偆側椺偼懡偔抦傜傟偰偄傞丅乧僀儞僪乕儖偼婓敄側帪偵偼夣揔側壴偺僯僆僀傪傕偮偑丄擹偔側傞偲暢擜偺僯僆僀偲側傝丄埆廘暔幙偺椺偲偟偰傛偔偁偘傜傟傞乿乮亀歬妎偺榖亁乯偱偁傞丅
丂傑偨廘偄偵偼丄
丂乽懠恖偺巕偳傕偺戝曋偺僯僆僀偼丄偼偭偒傝偲廘偄偲姶偠丄晄夣姶傪傕偮偑丄帺暘偺愒傫朧偺戝曋偺乫僯僆僀偼廘偄偗傟偳傕偝傎偳晄夣姶傪傕偨側偄乿乮亀擋偄偺壢妛亁乮崅栘掑宧挊丄挬憅彂揦丄1989乯乯
偲偄偆傛偆偵丄姶忣偑嫮偔摥偔懁柺傪傕偭偰偄傞丅
2亅2廘偄偺昞尰
丂歬妎偼尨巒揑側姶妎偱偁傝丄偦偺姶惈偵偼屄恖嵎偑戝偒偄偲偄傢傟偰偄傞偑丄歬妎偑旕忢偵塻晀偱僯僆僀悽奅偺宱尡偑朙偐偱偁偭偨嶌壠偲偟偰丄僼儔儞僗偺僄儈乕儖丒僝儔傗H丏僶儖僓僢僋偑抦傜傟偰偄傞丅椺偊偽丄亀偵偍偄偺楌巎亁乮傾儔儞丒僐儖僶儞挊丄嶳揷搊悽巕丒幁搰栁栿丄摗尨彂揦丄1990乯偵傛傞偲丄僶儖僓僢僋偼壠偵饽傞廘偄傪婥偵偟丄
丂乽僑儈幪偰偺廘偄丄憒彍偺偄偒偲偳偐側偄晹壆偵偙傕傞埆廘丄偦偙偵嫃偮偔撈恎抝偨偪偺敪嶶暔偱墭傟偰偟傑偭偨帠柋強偺嬻婥丄嬻婥偺捠傢偸晹壆偵摿桳偺廘婥丄恎懱偺偸偔傕傝傪偍傃偨儀僢僩偺傓偐偮偔傛偆側廘偄丄傎偙傝傑傒傟偺屆傃偨暻妡偗傗抃恲偐傜偨偪偺傏傞桘偺晠偭偨傛偆側廘偄丄巰懱埨抲幒偵偙傕傞廘婥乿
傪歬偓傢偗丄
丂乽壓廻壆偺乧傓偭偲偙傕偭偰丄陘偔偝偄丄桘偺晠偭偨傛偆側廘偄偑偡傞丅偧偔偧偔偡傞傛偆側廘偄丄偟傔偭傏偔旲偵偮偔廘偄偑J拝暔偵傑偱偟傒偰偄傞乧乿
偲丄廘偄傪條乆偵尵偄昞傢偟偰偄傞丅
丂擔杮偺嶌壠偱偼丄嶰搰桼婭晇偑亀嬛怓亁偺拞偱丄搶嫗偺奨偺僯僆僀傪塻偄歬妎偱師偺傛偆偵昤幨偟偰偄傞丅
丂乽梉曽偺奨偺擋偄偑晀姶偵旲岴傪偔偡偖偭偨丅乧壥幚傗僱儖傗怴姧彂傗梉姧傗悀朳傗噗噼傗孋杗傗僈僜儕儞傗捫暔偺擋偄偑丄擖傝傑偠偭偰奨偺側傝傢偄偺敿摟柧側偍傏傠偘側奊抧恾傪偆偐偽偣偨乿
2亅3丂僯僆僀偺庬椶
丂乽忋悈帋尡曽朄乿乮擔杮悈摴嫤夛丄1993擭斉乯偵傛傞偲丄廘婥偼丄
丂朏崄惈廘婥丗朏崄廘丄栻枴廘丄儊儘儞廘丄偡傒傟廘丄偵傫偵偔廘丄偒傘偆傝廘
丂怉暔惈廘婥丗憯廘丄惵憪廘丄栘嵽廘丄奀憯廘丄榤廘
丂搚丒偐傃廘丗搚廘丄徖戲廘丄偐傃廘
丂嫑廘丒側傑偖偝廘丗嫑廘丄側傑偖偝廘丄偼傑偖傝廘
丂栻昳惈廘婥丗僼僃僲乕儖廘丄僞乕儖廘丄桘條廘丄桘帀廘丄僷儔僼傿儞廘丄棸壔悈慺廘丄墫慺廘丄僋儘儘僼僃僲乕儖廘丄偦偺懠栻昳廘
丂嬥懏廘丗嬥婥廘丄嬥懏廘
丂晠攕惈廘婥丗悀奌廘丄壓悈廘丄撠彫壆廘丄晠攕廘
側偳偵暘椶偝傟傞偲偄偆丅
丂傑偨丄歬妎専嵏偵巊傢傟傞婎弨廘偼丄師偺傛偆偵昞尰偝傟偰偄傞丅
兝亅僼僃僯儖僄僠儖傾儖僐乕儖丗僶儔偺僯僆僀
僔僋儘僥儞丂丂丂丂丂丂丂丂丂丗徟偘偨僯僆僀
僀僜媑憪巁丂丂丂丂丂丂丂丂丂丗墭傟偨孋壓偺僯僆僀
兞亅傾儞僨僇儔僋僩儞丂丂丂丂丗搷偺僯僆僀
僗僇僩乕儖丂丂丂丂丂丂丂丂丂丗暢偺僯僆僀
僄僌僓儖僩儔僀僪丂丂丂丂丂丂丗壔徬昳偺僯僆僀
僼僃僲乕儖丂丂丂丂丂丂丂丂丂丗昦堾偺僯僆僀
dl亅僇儞僼傽乕丂丂丂丂丂丂丂丗従擼偺僯僆僀
僕傾僠儖僒儖僼傽僀僪丂丂丂丂丗僯儞僯僋偺僯僆僀
恷巁丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丗恷偺僯僆僀
偝傜偵丄埆廘杊巭朄乮徍榓47擭巤峴乯偱偄偆埆廘暔幙偼丄
丂傾儞儌僯傾丂丂丂丂丂丂丂丂丗暢擜廘
丂儊僠儖儊儖僇僾僞儞丂丂丂丂丗晠偭偨僞儅僱僊偺傛偆側僯僆僀
丂棸壔悈慺丂丂丂丂丂丂丂丂丂丗晠偭偨棏偺傛偆側僯僆僀
丂擇棸壔儊僠儖丂丂丂丂丂丂丂丗晠偭偨僉儍儀僣偺傛偆側僯僆僀
丂僩儕儊僠儖傾儗儞丂丂丂丂丂丗晠偭偨嫑偺傛偆側僯僆僀
丂傾僙僩傾儖僨僸僪丂丂丂丂丂丗惵廘偄巋寖偺偁傞僯僆僀
丂僗僠儗儞丂丂丂丂丂丂丂丂丂丗僈僗偺傛偆側僯僆僀
側偳偲昞尰偝傟偰偄傞丅
丂洕擜傗僩僀儗偺廘偄偼丄暢曋偺娷桳暔偱偁傞僀儞僪乕儖乮C6H7N乯傗僗僇僩乕儖乮C9H9N乯丄偁傞偄偼擜偺娷桳暔偱偁傞擜慺偑暘夝偝傟惗惉偟偨傾儞儌僯傾乮NH3乯偐傜敪偣傜傟傞傕偺偱偁傝丄乽暢廘乿偲偐乽暢擜廘乿偲偐偺尵梩偱昞尰偝傟傞丅
3丏壠偺拞偱偺廘偄
丂崅嫶弐晇偼1924擭挿栰導恴朘巗偱惗傑傟丄導撪奺抧偺彫丒拞妛峑偺嫵堳傪楌擟偟偨屻1981擭偵戅怑偟偰偄傞丅挊彂偵丄僄僢僙僀廤偺亀怱徾晽宨亁丄亀擔忢偺姶徿亁丄亀傆傞偝偲亁丄亀傆傞偝偲嘦亁丄亀傆傞棦怣廈忋恴朘亁丄亀傆傞棦怣廈恴朘亁側偳偑偁傞丅
丂帟壢堛偱偁偭偨晝偑昦婥偲側傝帿傔偨偨傔丄徍榓8擭彫妛峑4擭惗偺帪丄摨偠巗撪偺搾偺榚偺庁壠偵堷偭墇偟偰偄傞丅廫戙偺屻敿乮徍榓13乣19擭乯偵偼丄曌妛偲廇怑偺偨傔丄搶嫗丒恄揷偺恊愂偺壠傗夛幮偺椌乮搶嫗丒拞栰乯偵婑廻偟丄偦偙偱偼悈愻僩僀儗偺壎宐傪庴偗偰偄傞丅偦偺屻婣嫿偟丄嫵怑偵廇偄偰偄傞丅
丂傑偢丄恴朘巗撪偺壠偺媯庢傝曋強偺幚忣偲廘偄偺婰壇傪偙偺傛偆偵弎傋偰偄傞丅
丂乽搾偺榚偺庁壠偼丄壠偺彫偝偄偺偵墳偠偰曋捹偼戝偒偄時傪杽傔偨偔傜偄偱丄孼掜偺懡偄傢偑壠側偺偱丄捹偼偡偖偄偭傁偄偵側傝丄帪偲偟偰曋偑奜傊偁傆傟弌偟偨丅偦傟傪尒傞偺偼巕嫙怱偵傕偮傜偐偭偨丅偙偺曋偺媯傒庢傝偼丄戝榓嬫偺偁傞擾壠偲宊栺偟偰偁偭偰丄媯傒庢傝傪棅傒偵峴偔偲柍椏偱媯傒庢偭偰偔傟偨丅乧棅傒偵偄偔巇帠偼丄巹偺栶栚偵側偭偰偄偨偐傜偩乿
丂乽曋強帪戙偼丄偦偺廘婥偑曋強偐傜傕傟偰丄晹壆偄偭傁偄偵峀偑傝丄側偐側偐徚偊側偄丅帺暘偺帪偩偗偱側偔丄嵢偺帪傕丄丏擇恖偺巕嫙偺帪傕摨偠傛偆偵峀偑偭偨丅擇恖偑懕偗偰偼偄傞偲丄堦帪娫偖傜偄晹壆拞偑廘偭偰偄偨丅偦傟偑傗偭偲側偔側偭偨乿
丂偙偙偱丄乽偦傟偑傗偭偲側偔側偭偨乿偲尵偭偰偄傞偺偼丄曋強偑悈愻僩僀儗偵側偭偨偐傜偱偁傞丅偦偺帪偺姶寖傪偙偺傛偆偵昤幨偟偰偄傞丅
丂乽廫擭慜丄搾偺榚抧嬫偵傕奺壠掚偵壏愹偑堷偗丄摨帪偵壓悈摴偑偱偒偰丄曋強傪悈愻偵偱偒傞偲偄偆榖傪暦偄偰丄憗懍怽偟崬傫偩丅乧悈愻僩僀儗偵偡傟偽丄巹偺偄傒寵偆曋偺廘偄傪偐偖偙偲傕側偔丄捹偺拞偵偳傠偳傠偟偰偄傞曋偺偐偨傑傝傪尒側偄偱偡傓偺偩偐傜丄乧丅偄偪憗偔壏愹偲悈愻僩僀儗偺愝抲傪嬈幰偵埶棅偟偨丅乧弌偟偨偽偐傝偺偲偖傠傪姫偄偨暢偺偐偨傑傝偑丄僓傽乕偲棳弌偡傞悈偲嫟偵摏偺拞傊媧偄崬傑傟偰偄偔偺傪尒偰偄傞偲丄婥帩偪偑惏乆偟偰偔傞丅乮曋強偑廘偔側偄側傫偰曋強偲傕偄偊側偄側丅廘偔側偄曋強傪僩僀儗偲偄偆偺偐側乯丄側傫偰彑庤偵寛傔偰偄傞乿
4丏媯庢傝帪偺廘偄
丂偝傜偵崅嫶偼丄曋強偺媯庢傝嶌嬈拞偵曈傝偵棫偪崬傔傞廘偄偵傕晀姶偵斀墳偟丄師偺傛偆偵弎傋偰偄傞丅丂乽憢傪奐偗傞偲丄媯傒庢傝偺廘偄偑丄偳偭偲晹壆偺拞傊傛偣偰偒偰丄偁傢偰偰憢傪暵傔偨丅傢偑壠偺僩僀儗傪悈愻偵偟偰傕偆廫擭嬤偔側傞偲偄偆偺偵丄偙偺嬤強偺壠偵偼丄傑偩塹惗幵偱媯傒庢傝傪偟偰偄傞壠偑偁傞傛偆偩丅晽岦偒偵傛偭偰偼丄堦僉儘傕棧傟偰偄傞壠偺媯傒庢傝偺廘偄偑丄傢偑壠傑偱撏偔偙偲偑偁傞丅岾偄丄媯傒庢傝偵梫偡傞帪娫偼抁偄偺偱丄廘偄偑晹壆偺拞偵偨偩傛偭偰偄傞帪娫偼偦傫側偵挿偔偼柍偄乿
丂崅嫶偲摨條偵丄洕擜偺廘偄偵嫮偄姶庴惈傪帩偮偁傞壠掚偺庡晈偺怳傞晳偄傪徻嵶偵昤幨偟偨丄彮彈偺嶌暥傪亀捲曽嫵幒亁乮朙揷惓巕挊丄栘寋幮乯偐傜徯夘偡傞丅
丂乽掚偺棤栘屗偑偁偄偰扤偐偑擖偭偰棃偨丅彫曣偝傫偼枖丄岥傪逶偱墴偝偊偰丄乽傎傜丄棃偨丅朙揷偝傫丄掑巕傕丄憗偔丄憗偔乿偲偄偭偰帺暘偐傜愭偵壠傊擖偭偰偟傑偭偨丅巹傕壗偑壗偩偐傢偐傜側偄偱丄彫曣偝傫偺屻偵偮偯偄偰偍彑庤偐傜擖偭偨丅彫搰偝傫偑偍彑庤偲楲壓傪偟傔偨丅彫搰偝傫偵丄乽壗偁偵乿偲暦偔偲丄彫搰偝傫偼丄乽偍傢偄壆丄偍傢偄壆乿偲尵偭偰徫偭偨丅乧僈儃僢僈儃僢偲偍傢偄傪媯傓壒偑暦偙偊傞乿
丂岥傪逶偱墴偝偊偰偲偄偆乽偟偖偝乿偼偄偐偵傕彈惈傜偟偄乮恾亅1嶲徠乯丅偙偺壠偺庡晈偼嶌幰偺朙揷惓巕傕尵偭偰偄傞傛偆偵丄恖暲傒奜傟偰鉟楉岲偒偱偁偭偨偦偆偱偁傞偑丄曋強偺媯庢傝帪偺懺搙偼堦斒偵傕偙傟偲帡偨傛偆側偲偙傠偑偁偭偨偱偁傠偆丅

幨恀亅1丂暱庅偱媯庢傞丂乮乽僩僀儗峫丒洕擜峫乿傛傝乯

恾亅1丂旍壉偺塣斃丂乮乽儅儞僈柧帯丒戝惓巎乿傛傝乯
5丏奨妏偱偺廘偄
丂懞嶳掑栫偼1925擭搶嫗偵惗傑傟丄僐儈儏僯働乕僔儑儞榑傪愱峌偟捗揷弇戝妛偺島巘傪柋傔偰偍傝丄亀恖偼側偤怓偵偙偩傢傞偐亁乮KK儀僗僩僙儔乕僘乯側偳偺挊彂偑偁傞丅亀恖偼側偤擋偄偵偙偩傢傞偐亁偺乽偁偲偑偒偵偐偊偰乿偺崁偱丄
丂乽恖偦傟偧傟丄崱擔傑偱偺帺暘偺楌巎傪丄偵偍偄偱偮側偄偱傒傛偆偲偡傞偲丄寢峔偵偍偄偼婰壇偵巆偭偰偄傞傕偺偩丅偼偠傔偰尒偨傝丄暦偄偨傝丄枴傢偭偨傝丄怗偭偨傝偟偨婰壇偼偙偨偟偐偵嫮偄偑丄偵偍偄偼恖惗偵暿側忣弿傪忴偟偰偔傟傞丅偵偍偄偱丄敿惗傪捲偭偰傒傞偙偲傕柺敀偔丄偍偡偡傔偟偨偄乿
偲丄廘偄偵娭偡傞帺暘巎傪悇彠偟偰偄傞偑丄偦偺幚椺偲偟偰帺傜師偺傛偆偵彂偄偰偄傞丅
丂乽巹偺壠偺丄偦偺暬偼丄妱崌丄挿偐偭偨偐傜丄嬫偺洕擜偺媯庢壉偺堦帪揑廤愊応強偵側偭偰偟傑偭偨丅摉帪偼丄栶強偵暥嬪傪偄偭偨傝偡傞偙偲傕側偐側偐偱偒偵偔偄帪戙偱偁偭偨丅墶偵廫埲忋丄廲偵嶰抜偖傜偄愊傒忋偘偰丄媿偺壸幵偑偔傞傑偱丄堦丄擇擔曻抲偝傟傞偺偱丄嬤強偠傘偆偑偔偝偔偰丄偨傑偭偨傕偺偱偼側偐偭偨丅傓傠傫丄敄偄斅暬堦枃偱丄乮傢偑壠偺掚偺乯業抧偵傕偵偍偄偑廩枮偟偰偄偨偑丄偨傑偨傑偍拑夛偑廳側傟偽丄傕偆堊偡弍偼側偐偭偨乿
偲偁傞丅奨妏偐傜壠偺拞傊擡傃婑偭偰偔傞洕擜偺廘偄偵偼丄偍庤忋偘偱偁偭偨偙偲偑傛偔傢偐傞丅
丂崅嫶傕奨傪曕偄偰偄偰丄塹惗幵偑洕擜偺媯庢傝嶌嬈傪偟偰偄傞偲偙傠偵弌夛偄丄
丂乽嵟嬤偱傕奨偺儊僀儞偺捠傝偵塹惗幵偑巭傑偭偰偄偰丄偁偺旲傪偮偔偵偍偄傪偁偨傝堦柺偵傑偒偪傜偟偰偄偨丅偄傠偄傠帠忣偼偁傞偩傠偆偑丄傕偆偦傠偦傠柍偔側偭偰傕偄偄帪婜偠傖偁側偄偐偲巚偆丅乧偁偺塹惗幵傪巊傢側偔偰嵪傓偺偼壗帪偵側傞偙偲偐乿
偲丄庤尩偟偄嬯尵傪掓偟偰偄傞丅
6丏敤偱偺廘偄
丂懞嶳偼丄妛峑擾墍偱旍椏偲偟偰嶵偄偨洕擜偺廘偄傪嫮楏偵婰壇偟偰偄傞丅
丂乽帣摱偵丄堭傗戝崻傗壷巕傗層塟傗僩儅僩傪偮偔傜偣丄椦娫偱庼嬈傕傗偭偨丅偦偺崰偺旍椏偼恖娫偺洕擜傪棴傔偨嵟偨傞桳婡旍椏偱偁偭偨偐傜丄偦偺偵偍偄偼丄偄傑偱傕偗偭偟偰朰傟傜傟側偄乿
丂堦曽丄崅嫶偼偙傟偲偼媡偵丄偁傟傎偳栄寵偄偟偰偄傞洕擜偺廘偄偱偼偁傞偑丄帺暘偑媯庢偭偰敤偵嶵偄偨偦偺廘偄偵偼丄傓偟傠恊偟偄婥帩偪偑桸偄偨偲弎傋偰偄傞丅
丂乽徏杮偺恄屗偺壠偼崱偱傕曋捹偱丄乧傢偑壠偩偗偼暢擜傪旍椏偲偟偰丄敤偵傑偄偰偄傞丅嵢偼廡擇夞丄巹偼廡堦夞偙偙偵峴偔偺偑偄偄偲偙偩偐傜丄暢擜傕偨偔偝傫偼偨傑偭偰偄側偄偺偵丄巹偼峴偔搙偵曋捹偐傜媯傒偩偟偰偼敤偺寠偵擖傞丅乧堄抧偵側偭偰媯傒庢偭偰偼丄敤偵嶵偔丅偙偆偄偆嶌嬈偺帪偼丄暢擜偑懡彮庤偵偮偄偨偭偰偍偐傑偄側偟偩丅偁偺偵偍偄偑戝寵偄側壌偑丄偳偆偄偆偙偲偩傠偆偲斀徣偟偰傒偨丅乧暢擜偵懳偡傞偙偲揋偵懳偡傞偐偛偲偔偲側傞丅偦偺偔偣敤偱廘偆暢擜偵偼壗傜揋堄偼姶偤偢丄乧乿
丂敤偱偺洕擜偺廘偄偵懳偡傞崅嫶偺姶惈偑僩僀儗偵懳偡傞偦傟偲堘偭偨偺偼丄擾嶌暔偺廂妌傊偺婜懸姶偐傜偱偁傠偆偐丄偦傟偲傕丄曋強偵棴傑偭偨墭暔傪憒彍偱偒偨偲偄偆払惉姶偐傜偱偁傠偆偐丅
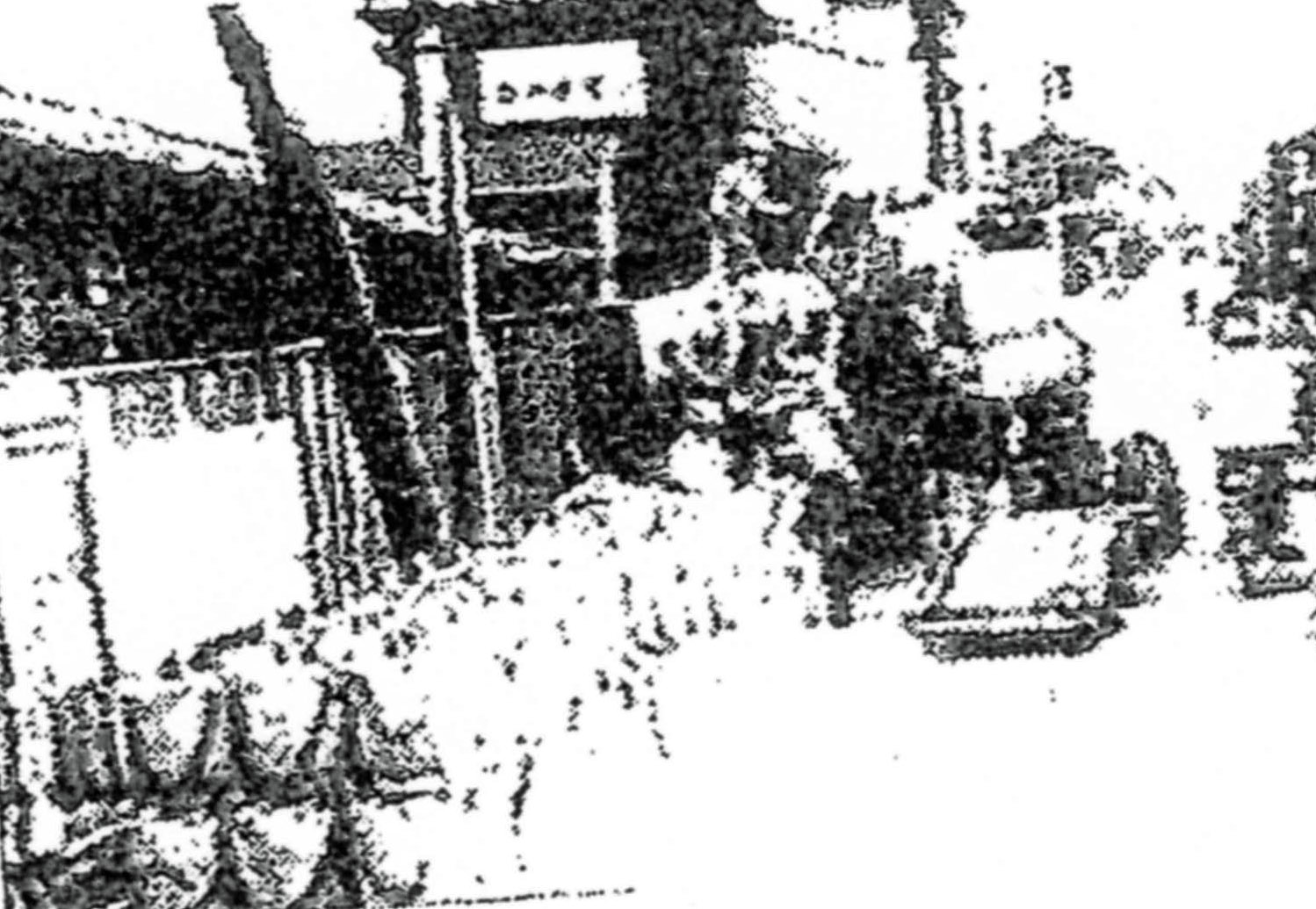
幨恀亅2丂旍壉偺壖抲偒丂乮乽僩僀儗峫丒洕擜峫乿傛傝乯
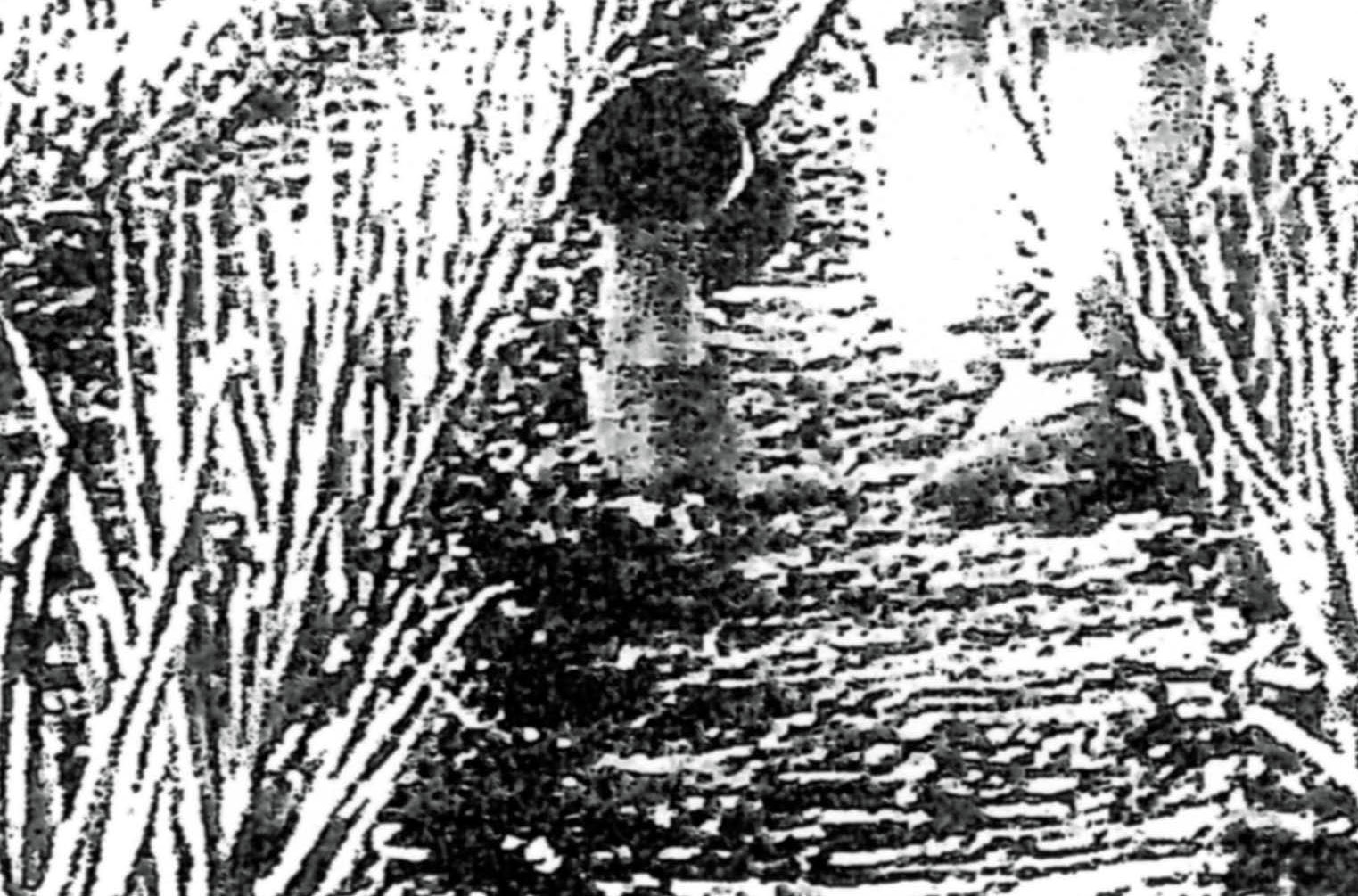
幨恀亅3丂洕擜偺巤旍丂乮乽僩僀儗峫丒洕擜峫乿傛傝乯
7丏偍傢傝偵
丂尰戙偼惔寜巙岦偑恑傒丄柍嬠揑側娐嫬傪摉慠偺偛偲偔嫕庴偟偰偄傞丅廘偄偵娭偟偰傕慠傝偱偁傝丄偪傚偭偲偱傕庤擖傟偺埆偄岞廜僩僀儗偵擖偭偨傝偡傞偲丄巚傢偢堦弖懅傪巭傔偨傝偡傞丅洕擜側偳偺晄夣側廘偄偵懳偟偰晀姶側偺偼僸僩偵旛傢偭偨杮擻偱偼偁傞偑丄廘偄偺婰壇偵偼姶忣偑夘嵼偡傞偑備偊偵丄婰壇偵巆偭偰偄傞廘偄傪嵞尰偡傞偵偁偨偭偰偼儕傾儖側昞尰偑偟偵偔偄偺偱偼側偐傠偆偐丅
亂嶲峫暥專亃乮杮暥拞偱柧婰偟偨傕偺傪彍偔乯
1乯埨揷惌旻挊丗暯埨嫗偺僯僆僀丄媑愳峅暥娰丄2007
2乯偍偄偟偄悈傪峫偊傞慡曇丗悈摴悈偲偵偍偄偺偼側偟丄媄曬摪弌斉丄2001
